今回の記事は
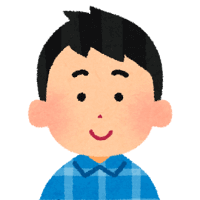
「よく、hear (that) S+Vはhear O+Cに書き換えができると言いますが、そもそもこの2つには違いというものがないのでしょうか?」
という疑問に答えた内容になっています。
●こんにちは、まこちょです。
英語を学習していると「知覚動詞」という英単語を耳にする機会があるかと思います。hear(聞く) / see (見る)/ feel(感じる)などが代表的ですね。
この知覚動詞なのですが、hear+O+C、ようするにSVOCの5文型を取ることで有名なのですが、軽くhear O+Cといっても、Cの位置に来る形はさまざまな形があるんですね。
ざっと挙げただけでも、知覚動詞のCの位置に来るものは現在不定詞(原形)/ 現在分詞(~ing) /過去分詞(~ed)などたくさんあります。もちろんそれぞれの形を会得しておくのは必須ですね。
【hear+O+Cのいろいろな形】
① hear+O+ 原形不定詞(原形)
→ 「【Oが~する】のを聞く」
例①
He heard her sing.
「彼は彼女が歌うのを聞いた」
② hear+O+ 現在分詞
→ 「【Oが~している】のを聞く」
例②
I heard him playing tennis.
「私は、彼がテニスをしているのを聞いた」
③ hear+O+ 過去分詞
→ 「【Oが~される】のを聞く」
例③
I heard the door opened.
「私は、そのドアが開けられるのを(音を)聞いた」

知覚動詞の具体的な訳し方を学習したい方は以下の記事をまずはのぞいてみましょう。これで知覚動詞の解釈方法のすべてが分かります。

いや、今回のテーマは知覚動詞のCの位置に来る種類についての記事ではありません(笑)
実は上記にご紹介したhear+O+Cなのですが、これらはすべてhear that S+Vに書き換えられるのです。例えば例①ですが以下のように変形可能です。
例①
He heard her sing.
=He heard (that) she sang.
この事実は意外と知っている方も多いのですが、実はこの2つ、微妙にニュアンスが異なることはご存じでしょうか。「え?同じ意味じゃないの?」と思った人!以下の記事の内容を知らないと、とんでもない誤解を生じてしまうかもしれません。
そこで今回は「知覚動詞+O+C」と「知覚動詞 that S+V」の微妙なニュアンスの違いについて徹底解説!以下の記事をお読みいただくと、次の点であなたの英語力は向上します。
ぜひマスターしていただいて、今後の英語学習にお役立てください。
このhearは「知覚」と「伝聞」がある

実はhear O+Cとhear that S+Vは状況が全く異なる意味合いになることは覚えておきましょう。
hear O+Cの場合=「知覚」
知覚動詞がSVOC文型を取る場合、この場合は文字通り「知覚」構文です。例えば次の例を見てください。
例
He heard her shout.
「彼は彼女が叫ぶのを聞いた」
He(S) heard(V) her(O) shout(C).
この場合SVOCの第5文型を取っていますが、この時は主語であるHeは【直接】彼女の叫びを聞いています。彼の耳が彼女の「キャー!」という声を直で聞いたということです。
ところがこの文をthat節に変形させてみましょう。そうするとどうなるのでしょうか。
He heard (that) she shouted.
こうなると彼は直接耳で彼女の叫び声を聞いたわけではありません。彼女が叫んだことを【間接的に】聞いたのです。例えば友人から聞いたとかね。
つまりthat節になるとthat節の内容が【伝聞】になるんです。まるで主節の文と従属節の文の間にあるthat節が防波堤みたいにクッションになるんですね。
まとめると
● hear+O+C
→ 【知覚】OがCであることを直接的に聞いている
● hear (that) S+V
→ 【伝聞】SがVするのを間接的に聞いている
ちょっと練習してみましょう。例えば「誰かが近づいてくる音が聞こえた」を英訳する場合はどうでしょうか。
この音は直接「耳」で聞いているんだな、ということが分かれば仮にhearを使うとしてもthat節は不適当だと分かりますよね。したがって
◎ I heard someone approaching me.
× I heard (that) someone was approaching me.
と上の文がより日本語の意味をしっかり伝えているのがお判りいただけると思います。
知覚動詞はなぜ進行形にできないのか
最後に知覚動詞について注意すべきポイントについて触れておきますね。
知覚動詞を学習する際に必ず学習することの1つに知覚動詞は進行形にできないというルールがあるのですが、なぜ知覚動詞は進行形にできないのでしょうか。
この時、単純にhear「聞こえる」やsee「見かける」の動詞は状態動詞だから進行形にできないのだ、と暗記一辺倒に考えずにしっかりと理詰めで押さえておくとよいでしょう。
進行形とは自分の意志で行うもの
進行形というのは自らの意思で一時的に「~している最中だ」とできるような動詞について用いられます。
この「~している最中だ」というのは、言い換えると「はじめ」と「終わり」があることは一目瞭然です。というか「はじめ」と「終わり」がなければ、そもそも「~している最中だ」ということが出来ません。例えば
例
I am studying English.
「私は今英語を勉強している最中だ」
この文はstudyを使った英文ですが、studyは進行形にすることが出来ます。なぜなら「勉強する」という行為は
「勉強はじめ」
(始めるぜ!という意志)
↓
「勉強している途中」
(まだまだやるぜ!という意志)
↓
「勉強終わり」
(やめるぜ!という意志)
という「はじめ」「最中」「終わり」が必ずワンセットであるからです。そしてこの過程のなかで必ず関わるのが「行為者の意志」。
「意志」ですからその気になったらやめることが出来ます。前提としてはじめと終わりがあるけれど、その気になったらいつでも途中でやめられる、このような動詞に対して進行形を使うことが出来るんですね。ちなみにこのような動詞を「動作動詞」といいます。
それに対して知覚動詞は「意思」が入りません。簡単に言ってしまうと行為者の意思に【関係なく】五感を刺激する動詞を知覚動詞というんです。
意思がないのですから「~しよう!」という「はじめ」もありません。勝手に意識の中に入ってくるんです。しかも「はじめ」がないのですから「最中(途中)」という概念もありません。したがって行為者の意志でやめることもできないのです。
「途中」の概念がないのですから進行形表現なんてあるわけがないんですね。
こういった動詞を総称して「状態動詞」といいます。この状態動詞のカテゴリの中に「知覚動詞」も含まれているんですね。
この状態動詞と動作動詞についてまとめると以下のようになります。
● 動作動詞
①進行形にできる
②意思がからむ
③途中でやめられる
●状態動詞
①進行形にできない
②意思がからまない
③(外的要因がない限り)途中でやめられない

※ここからは応用ですが、状態動詞でもある条件が重なると「進行形」にすることが出来ます。以下の記事に詳しくまとめましたので、のぞいてみてください。

知覚動詞のニュアンスの違いについて:まとめ
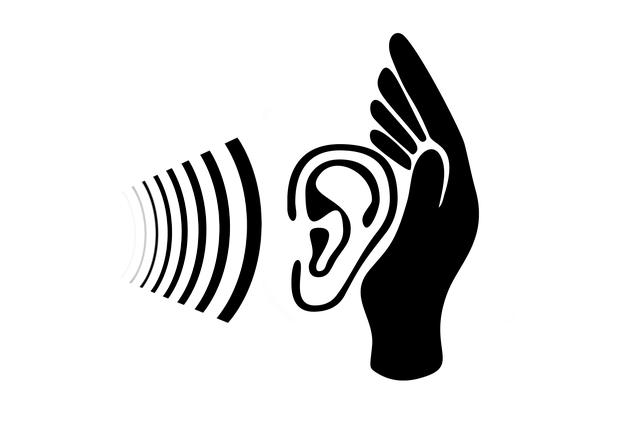
今回は知覚動詞の後ろに続く形によって意味合いが変わるというお話をまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。
知覚動詞+that S+Vという形になったとき、thatがクッションとなってthat節の内容を直で耳にしたということにはならず、誰かからの又聞き、つまり「伝聞」になるというのは意外に気づかないポイントですのでぜひものにしてくださいね!
また会いましょう。

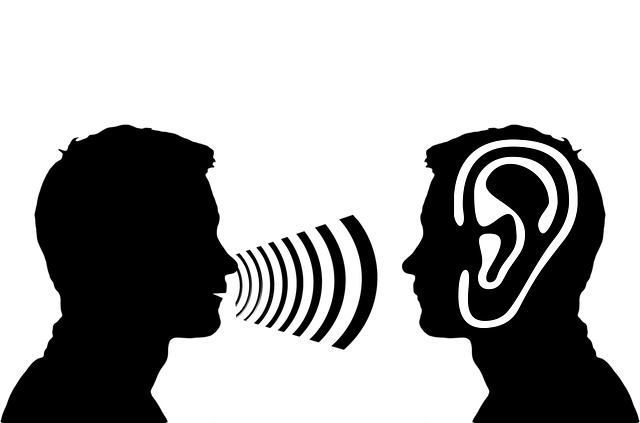


コメント