この記事は

「実際に英文を読んでいると倒置しているかどうかがよく分らないことがあります。倒置構文に気づくにはどういったところに注意すればよいでしょうか?実際に練習問題を通じて教えてほしいのですが」
と悩んでいる英文リーディング学習者に向けて記事を書いています。
● こんにちは、まこちょです。
英語の「倒置構文」はよほど難しいのか、相変わらず質問が絶えません。特に長文中に出てくる倒置構文に全く気づかないことが多いというんです。
当ブログでも「倒置」についての考察はこれまでも何回か記事にしています。倒置とは何なのか?という点からご紹介していますので、もし集中的に学習したい場合は以下の「倒置に関するカテゴリ一覧」をのぞいていただければ幸いです。
ところがこういった「倒置」についての記事を熟読したのにも関わらず、実際に英文を読むと、その文が倒置をしていると気づかないことがあるというのです。
この気持ちはよくわかります。私もそうですが心のどこかで「倒置する場合がある!」と思っていてもなかなかそれを実践投入できないのはよくあることですからね。頭ではわかっていても….という感じでしょうか。
そこで今回は実際の英字新聞・雑誌から英文を抜粋して、実際に「倒置」というのはどのように表現されているのか、英文を通じてみなさんと考えてみようかなと。
抜粋した英文は雑誌TIMEからで、たったの1文です。ですが、そんなに簡単に読めるような構造ではありません。
ですが英語学習は多読も大事、そして「精読」も非常に重要です。たまには骨のある英文をじっくり読んでいただければと思います。
今回の記事を最後まで読んでいただけると、次の点であなたの英文解釈能力は向上します。
▶基本文型(SVOC)を身につけることが非常に重要であることが分かる
倒置の練習問題
どうですか?TIMEの英文くらいになると、構文も複雑でなかなか骨の折れる英文がガンガン出てきます。なんか大学入試問題に出てきそうな英文ですよね。
しかも今回のテーマの「倒置」なんてものがからんでくるとそれはそれは…この文章をサラッと読める方は相当な英語力の持ち主ですね。
解説
いきなりですが試練がやってきます(笑)importantは形容詞ですので主語(S)になれないことに気づいたでしょうか。

英文の(S)と動詞(V)を見つけるための基本姿勢は以下の記事で学習できますよ!

wasの前に「名詞」がありませんから、この時点で「倒置」しているのでは?と疑えることが重要ですね。

そして動詞の前に主語(S)がない場合は動詞の後ろにあるというルールも同時に思い出しましょう。

Far more important(C) was(V) his finding out(S)…
と捉えられている方は読めている証拠です。つまりこの文はCVSといきなり倒置しているんですね。
訳「それよりはるかに重要だったのは、…を人類が発見したことだった」

続いて
… that the noises he makes in his throat when he wishes to express some emotion…
このthatがいわゆる「あの」の代名詞でないことは、後ろの名詞にtheがついていることから明らかです。そう、このthatは節を作るthat。
節ですから後ろはS+Vと文が来ることになりますので、そのつもりで読んでみると、最初に出てきた前置詞のついていない名詞を(S)と置き
… the noises(S) he makes in his throat…
the noisesの動詞(V)が出てくるかと思ったらhe makes in his throatと新たな文が出てきてしまいます。
ですがmakesが他動詞にもかかわらず後ろに名詞がないことに着目し、
… the noises(S) ⇐ [he makes Oがない in his throat]…
the noisesとheの間に「目的格の関係代名詞」が省略されていることに気づき、後ろのwhen節をまとめて
the noises(S) ⇐ [he makes in his throat (when he wishes to express some emotion)] could be developed(V)
とcould be developedと動詞を発見することができた人はお見事です!
- throat「のど」、
- make noises「音を発する」
- express some emotion「なんらかの感情を表現する」
訳「それよりはるかに重要だったのは、なんらかの感情を表現したいときにのどで発する音を発達することができるということを人類が発見したことだった」

英文中の名詞の役割を考えることは英文リーディングの重要なポイントの1つ。あわてずにしっかり押さえましょう!

後半は
… could be developed into a system (which he could use to communicate complex ideas to his fellows)
a systemは「体系」。どんな体系なのかをうしろから関係代名詞which以下で「説明」してくれそうです。
- to communicate「伝達するために」
- complex ideas「複雑な観念」
- fellow「仲間(ここでは他の人間)」
- A developed into B「Aを発展させてBにする」
訳「はるかに重要なのは、なんらかの感情を表現したいときに、のどで発する音を発達させ、複雑な観念をほかの人間に伝えるために使える体系にできるということを人類が発見したことだった」
いやぁ…毎回毎回、英文がこのくらいのクオリティだと、本当にしんどい!そう思えるような英文でしたね(笑)
あとがき

今回の英文はCVSと「倒置」している英文だったのですが、なぜこのような構造になったのかというと、主語(S)、つまりここでは his findingにthat節がくっついてしまって、全体として主部の部分が非常に長くなってしまったことにより起こった「倒置」だったんですね。
英文は主語が必要以上に長い場合は、動詞との距離が離れてしまいますので非常に読みにくくなってしまいます。
His finding(S) out [that ~ ] was(V) far more important(C).
それを避けるために主語を動詞の後ろに配置することによって、読みにくさををカバーしたのがこの英文だったのです。
英文は主語が長くなってしまうと非常に読みにくいですが、ピリオド近くが長くなるのは一向に構わないのです。
Far more important(C) was(V) his finding(S) out [that ~].
倒置が英文で発生するのは必ず何らかの意図があります。今回の英文もしっかりと意図を組んで、必然としてこういった英文の構造をしているのだ、ということが分かっていただけたらと思います!
どんどん英文を読んで、使える英文法の習得を目指してくださいね!
また会いましょう。
なお、倒置について徹底的に学習したい方は以下のカテゴリー一覧をのぞいてみてください。英文リーディング上、特に重要な形を集中的に学習することができます。
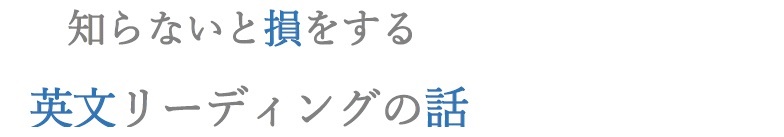





コメント